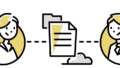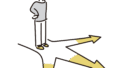質問:相続対策として、生前贈与はどのようにするのが良い?
親の相続対策のため生前贈与をした方が良いのか、どのような贈与方法が良いのか、
教えてください。
答え:贈与の方法は、大きく分けで2通り。相続対策として、まずはどんな財産を、どれくらい持っているのかを把握しましょう。
相続対策をした方がいいのか……そう考えたものの、どこから”対策”したらよいか
わからない。そういう方も多いと思います。
相続対策、というと相続『税』対策と思いがちですが、税金がかからない場合でも、
もめることはあります。
まずは、被相続人(亡くなって財産を残す側)となる人が、『何を』『どれだけ』財産を
持っているか、税金がかかりそうか、そして『誰に何を相続させるつもりか』を早い
段階で把握し、話し合っておくことが大切です。
そのうえで、『税』の対策を考えましょう。
「生前贈与って、やったほうがおトクだよね?でも、どうやってやるのがおトクなの?」
という疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
生前贈与は、確かに有効な相続対策の一つですが、方法しだいでは相続時に税負担が増えてしまうことも。2024年の税制改正を踏まえ、生前贈与の基本から具体的な活用方法までを解説します。
基本:相続対策はなぜ必要?
2015年以降、相続税の基礎控除額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へと大きく減少しました。これに伴い、相続税の課税件数が増え、税額も上昇しています。そこで、相続対策を必要をする人も増えます。
対策のひとつとしてする生前贈与には税金がかかりますが、その贈与方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」2つの方法があり、その他税負担を減らす制度がいくつか存在します。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合った制度を選ぶことが大切です。
相続対策のポイント
- 「相続時に課税される財産を減らすこと」
相続税の税額は、財産が多ければ多いほど(財産の価額が高いほど)税率が高くなる「超過累進課税」という仕組みになっています。生前贈与は、この「課税財産を減らす」ための有効な手段となります。ただし、贈与された財産には「贈与税」がかかります。贈与税は相続税よりも税負担が大きくなる可能性があるため、非課税枠を上手に活用することが重要です。 - ご家族が納得できる財産の分け方にすること
相続対策を考える際は、税金を減らすことだけでなく、遺されたご家族が円満に財産を分けられるようにすることも重要です。特定の親族に財産を多く渡したい場合でも、他の相続人の「遺留分(最低限受け取る権利)」を侵害しないかなどを考慮しながら進める必要があります。 - 相続対策は早めに計画し、実行すること
認知症などで判断能力が低下してしまうと、有効な対策がほとんどできなくなる可能性があります。
生前贈与の制度①:暦年課税
《暦年課税制度とは》
暦年課税制度は、1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからない制度です。この110万円は「基礎控除」と呼ばれています。
• 基礎控除:年間110万円までが非課税です。
• 非課税枠の活用:例えば、毎年110万円ずつ10年間贈与すれば、合計1,100万円を贈与税なしで渡す ことができます。これにより、将来の相続財産を効果的に減らすことができます。
• 対象者:贈与する人、贈与を受ける人ともに制限がありません。
• 税率:基礎控除額を超えた部分には、贈与額に応じた累進税率が適用されます(10%〜55%)。
《メリット》
• 手軽に少額を非課税で贈与できる
・ 贈与税を支払うことなく、計画的に数千万円もの財産を移転できる可能性がある
• 贈与相手の制限がない:親子、夫婦間だけでなく、兄弟間や友人など、誰に対しても利用できる
《デメリットと注意点》
• 生前贈与加算(持ち戻し期間の延長)=7年さかのぼって相続財産に戻される
以前は相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算されていましたが、令和6年1月1日以降の贈与から段階的に加算対象期間が7年間に延長されます。この期間に贈与された財産は、相続時に相続財産として計算されます。
• 「定期贈与」とみなされるリスク
毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、「最初からまとめて贈与するつもりだった」とみなされ、非課税枠を超えた部分に贈与税がかかる可能性があります。これを避けるためには、贈与の時期や金額を変えたり、贈与契約書を毎年作成したりすることが有効です。
• 「名義預金」とみなされるリスク
子や孫名義の口座に送金しても、受贈者本人がその事実を知らない、あるいは親が口座を管理しているなど、贈与が成立していないと判断されると、贈与は無効となり、贈与者(被相続人)の財産として相続税の対象になってしまいます。
生前贈与の制度②:相続時精算課税
《相続時精算課税とは》
特定の人(原則、60歳以上の親や祖父母)から特定の人(原則、18歳以上の子や孫)への贈与に利用できる制度です。
• 特別控除額
累計2,500万円までが贈与税非課税となります。この枠を使い切るまでは、何度か贈与しても贈与税はかかりません。
• 基礎控除額の新設
令和6年1月1日以降の贈与から、年110万円の基礎控除が新設されました。これにより、年間110万円までの贈与であれば、2,500万円の特別控除枠とは別に非課税となり、相続時に相続財産に加算されることもありません。110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除を超えた金額に対して、一律20%の贈与税が課されます。
• 「相続時」に精算
贈与時には贈与税がかかりませんが、贈与した人が亡くなった時に、これまでの贈与額を相続財産に加えて相続税を計算します。
• 相続時の扱い
贈与された財産は、贈与者が亡くなった際に、贈与時の評価額で相続財産に加算され、相続税の計算が行われます。すでに支払った贈与税がある場合は、相続税と相殺され、もし贈与税の方が多ければ還付されます。
• 届出が必要
この制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署に届出が必要です。
• 撤回不可
一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与については、暦年課税制度には戻れません。
• 課税の先送り
贈与時には非課税でも、最終的には相続税の対象となるため、「課税の先送り」と考えることができます。
《メリット》
• 短期間で多額の財産を非課税で移転できる:暦年課税よりも一度に大きな金額を贈与できるため、早期に相続財産を減らしたい場合に有効です。
• 将来値上がりする可能性のある財産に有利:贈与時の評価額で相続財産に加算されるため、贈与後に不動産や株式が値上がりしても、値上がり分には相続税がかかりません。
• 年間110万円の基礎控除の新設で使いやすく:2024年からは、年間110万円までの贈与が相続時に持ち戻されないため、計画的な贈与に活用しやすくなりました。
• 複数の贈与者からの使い分け:親と祖父母など、贈与者ごとにこの制度を選択できるため、それぞれからの贈与で非課税枠を有効活用できます。
《デメリット・注意点》
• 一度選択すると暦年課税に戻れない
• 「小規模宅地等の特例」と併用できない:これが不動産の生前贈与を考える上で重要な注意点です。
※「小規模宅地等の特例」とは、例えば被相続人が住んでいた自宅の敷地などの場合、最大330㎡まで評価額を80%も減額できる等の制度です。この特例は生前に相続時精算課税制度を利用して贈与された宅地には適用できず、結果的に相続税が高くなる可能性があります。
• 建物や車など、時間の経過とともに価値が下がる可能性のある資産を贈与した場合、相続時に贈与時の高い評価額が適用されるため、かえって税負担が重くなることがあります。
• 不動産贈与時のコスト:不動産を贈与する際は、贈与税以外にも登録免許税や不動産取得税が発生し、これらの税率は相続で取得するよりも高く設定されているため、大きな負担となるかもしれません。
• 他の相続人との不公平感:特定の相続人に多額の贈与を行うことで、他の子や孫から不満が出るリスクも考慮する必要があります。
どちらの制度で贈与をするのが良いのか?
所有している財産の総額や種類によって、最適な贈与方法は異なります。
- 財産総額が相続税の基礎控除額を下回る見込み場合
相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。
例えば、法定相続人が1人の場合、3,600万円までが非課税となります。
財産総額がこの基礎控除額を下回る見込みであれば、相続税はかかりません。
この場合、無理に生前贈与を行う必要性は低いかもしれません。
もちろん、自分の財産をはやく子や孫に渡して有効活用してもらいたい、という場合は、非課税枠を有効に使って贈与するのが良いでしょう。 - 財産総額が相続税の基礎控除額を超える場合
相続税がかかる見込みがある場合は、生前贈与が有効な相続対策となります。
《パターン1》少額の財産を長期的にコツコツ贈与したい場合
⇒暦年課税の利用が向いています。
• 方法:毎年、年間110万円の非課税枠内で、子や孫に現金を贈与します。
• 成功のポイント:「定期贈与」とみなされないよう、毎年贈与のたびに贈与契約書を作成し、金額を少しずつ変えるなどの工夫をしましょう。
・贈与の事実を受贈者本人に必ず知らせ、「あげます・もらいます」の合意をしっかり形成してください。
・贈与された財産は、受贈者自身が管理するようにします。
《パターン2》多額の財産を短期間で移転したい、または将来値上がりしそうな資産を贈与したい場合
⇒相続時精算課税制度の利用を検討します。
• 向いている資産:業績拡大が見込まれる会社の株式など、将来的に値上がりが予想される財産の贈与に特に有効です。
• 節税効果の理由:この制度で贈与された財産は、相続時に贈与時の評価額で加算されるため、その後の値上がり益に対して相続税がかからないメリットがあります。
• 多額の財産を一度で贈与できる:贈与を受ける人がまとまった資金を必要としている場合に有効です。新設された年間110万円の基礎控除を毎年活用すれば、2,500万円の枠を超えても一部非課税で贈与が可能です。
• 注意点:不動産の贈与を検討している場合、「小規模宅地等の特例」が適用できなくなるという大きなデメリットがあることを十分に理解しておきましょう。また、不動産取得税や登録免許税といった移転コストも相続より高くなるため、総合的な判断が必要です。
《パターン3》あえて「少額の贈与税」を支払う
メリット:年間110万円をわずかに超える金額を贈与し、少額の贈与税を支払うことで、贈与の意思を明確にし、「定期贈与」とみなされるリスクを低減できる場合があります。
向いているケース:計画的な贈与で「定期贈与」リスクを避けたいが、大きな贈与税は避けたい方。
特定の目的のために非課税で贈与したい場合
特定の目的のためには、大きな非課税枠が設けられている特例制度があります。
これらは暦年課税や相続時精算課税制度と併用できるものも多いです。
- 住宅取得等資金の贈与の特例
親や祖父母から子や孫へのマイホーム購入・新築・増改築のための資金援助に適用されます。
最大1,000万円(省エネ等住宅の場合)または500万円(一般住宅の場合)まで非課税になります。
この特例による贈与は、生前贈与加算の対象にはなりません。 - 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与):
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金の贈与に適用されます。
基礎控除110万円とは別に、最大2,000万円まで非課税で贈与できます(合計2,110万円)。
この特例による贈与も、生前贈与加算の対象にはなりません。 - 教育資金の一括贈与の特例:
親や祖父母から30歳未満の子や孫へ、教育資金を目的として贈与する場合に適用されます。
金融機関を経由するなどの条件を満たせば、最大1,500万円まで非課税になります(学校以外の費用は500万円まで)。
この特例による贈与も、原則として生前贈与加算の対象にはなりません(死亡時の残額は除く)。 - 結婚・子育て資金の一括贈与の特例
親や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫へ、結婚・子育て資金を目的として贈与する場合に適用されます。金融機関を経由するなどの条件を満たせば、最大1,000万円まで非課税になります(結婚費用は300万円まで)。
この特例による贈与も、原則として生前贈与加算の対象にはなりません(死亡時の残額は除く).
その他の注意点
生前贈与以外の相続対策や、相続全般にわたる注意点も押さえておきましょう。
《田舎の土地相続リスク》
田舎の土地は、維持費(固定資産税、メンテナンス費用など)もかさむ場合があります。売却も難しいことが多く、結果として「負動産(負債となる不動産)」になるケースも珍しくありません。相続放棄をしても、その土地を占有している場合(例えば、実家に住んでいた場合など)は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、管理義務が残る可能性があります(2023年4月の民法改正で明確化)。
《遺留分への配慮》
遺産を相続する権利を持つ法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。特定の相続人への生前贈与額が多すぎると、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があり、トラブルにつながることもあります。
まとめ
生前贈与は、相続税対策として非常に有効な手段ですが、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶか、いくらずつ贈与するのかは、ご自身の財産状況やご家族の状況によって最適な方法が異なります。
特に2024年の税制改正により、制度の使い勝手や注意点も変わっています。
それぞれのメリット・デメリットや注意点を理解し、ご自身の家族構成、資産の種類と総額、そして将来の展望に合わせて、最適な対策を選ぶことが成功の鍵となります。相続税がかからない場合も、どう遺産を分けるかは大切な問題です。早めに準備を始めることで、親族の皆が納得できる「相続」に向けて対策をしていきましょう。
実務よもや話
相続税の申告の仕事は、年に1~2件でした。
(地方で、相続専門ではない個人税理士事務所勤務時代)
生前贈与は、主に非上場株式、土地、現金の計画的な贈与が主でした。
少ない件数ながら、「もめる」という場面に遭遇しました。
相続(亡くなって)からもめるのはもちろん、生前贈与においても、本人とご家族の意向や
相続に対する思いにずれがあることはしばしば。
相続税の負担をいかに少なくするか、よりも、
財産を持つ本人とご家族がいかに納得し、望む形で財産をわけるか、
相続後の生活や会社の承継に支障が出ない形で財産をわけるか、
そのあたりが重要なのだと実感します。
※本記事は2025年7月時点の法令・制度に基づいて執筆しています。内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の事情に応じた法的助言を行うものではありません。万が一、記事の内容をもとに行動された結果として損害などが生じた場合でも、筆者としては責任を負いかねますこと、あらかじめご了承ください。