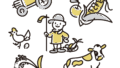質問:令和7年の年末調整、変更点や気を付けることを教えてください。
今年の年末調整、また変わったところがあると聞きました。
正直、憂鬱というか、不安というか……
どこが変わったのか経理担当者が気を付けること、
また従業員に早めに準備してもらうことがありますか?
答え:書式の変更、基礎控除等の引き上げ、それに伴う扶養の範囲の変更、などがあります。扶養親族のいる従業員には特に周知しましょう。
毎年、必要な書類が増えていく年末調整。税理士も、憂鬱になってしまいます、はい。
令和7年は大幅に変わっています
・まず、書類の様式の変更があります。
・そして、基礎控除や給与所得控除の金額が引き上げ
・引き上げに伴い扶養の範囲が変わる
・19歳~22歳の扶養親族に『特定親族特別控除』が新設
といった変更点があります。
憂鬱……ですが年末調整実務の季節はやってきます。
令和7年分の年末調整における変更点と、気を付けることをまとめていきます。
経理担当者だけが把握していても、うまく進まないのが年末調整。
従業員の方にも周知し(特に扶養しているご家族のいる方は必須)、
必要な書類や数字の把握を早めにしていきましょう。
令和7年年末調整、主な変更点
▶書類の様式変更
1.「基・配・所」の3種統合様式に、新設の「特定親族特別控除申告書」が追加
→1枚で4つの申告ができる様式に変更。
給与所得者の『基・配・特・所』申告書」という長~い名前の書類になりました。
略して「基配特所(きはいとくしょ)」と覚えましょう。
2.給与所得者の扶養控除等申告書(通称:マル扶)
→簡易な様式としても利用できるようレイアウトを修正(軽微な変更です)。
▶基礎控除、給与所得控除の引き上げ(に伴い扶養の範囲が変わる)
1.基礎控除額が「あなたの収入」で決まる時代へ!
→これまで多くの人が一律48万円だった基礎控除額が、令和7年からは収入に応じて変わります。
低収入の方ほど控除額が増え、高収入の方は減るという、なんとも世知辛いルールです。
• 給与年収200万4千円未満:95万円
• 給与年収200万4千円以上475万2千円未満:88万円(特例加算額含む)
• 給与年収475万2千円以上665万5千円以下:68万円(特例加算額含む)
• 給与年収665万5千円以上850万円以下:63万円(特例加算額含む)
• 給与年収850万円超:58万円
※上記には令和7年と令和8年の2年間限定で加算される特例加算額が含まれています。
➡令和6年までは、多くの人(給与収入でいうと2,595万円以下)が基礎控除48万円だったので、従業員から提出された用紙の基礎控除額の欄が空白でも、まあ48万で間違う可能性は低かったです。しかし、令和7年からは上記のように細かくきざまれているので、本人が何も書かないから会社の給与だけで控除額を計算したら実は副業収入があった、なんて場合は基礎控除額でミスする可能性がでます。怖いですね。
2.給与所得控除(給料収入から控除できる金額)
➡55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
3.「扶養の壁」が103万円から123万円へパワーアップ!
➡これまで年収103万円以下だった扶養の壁が、給与収入のみの場合、123万円以下に拡大。
ただし、社会保険の130万円の壁は健在。こっちは崩れない鉄壁の壁なので、ご注意を!
▶大学生年齢に新しく「特定親族」登場!
19歳から22歳の扶養親族に「特定親族特別控除」が新設されます。子どもの年収123万円を超えても、188万円までなら親の税金が安くなる新しい枠です。さらに、この年齢層の社会保険の壁も150万円に拡大されます。
▶住宅ローン控除の簡素化
2年目以降の住宅ローン控除の適用で、「調書方式」が導入されます。これにより、税務署から送られてくる控除証明書を提出するだけでよくなり、金融機関からの借入金年末残高証明書の添付が不要になります。
※借入先の金融機関が「調書方式」に対応しているか確認が必要になります。
経理担当者の準備(周知と書類チェック)
とにかく、今年はいつもより慎重に、そして最新の情報をキャッチアップしてください。
また、従業員からの「これってどういうこと?」という質問攻めにも備えましょう。
▶社員への周知徹底&問合せ対応
- 特定親族特別控除について従業員へ案内
→19歳から22歳の学生などが対象となる扶養親族について申告漏れがないか確認。 - 令和8年分の扶養控除申告書(マル扶)には「源泉控除対象親族」という新しい仲間を記入する欄も。
- 扶養親族の所得基準が変更されるため、従業員からの問い合わせが増える可能性があります。
- 住宅ローン控除の調書方式への対応
→新しい提出方法について従業員への説明や、受け付ける書類の確認が必要です。
▶新様式対応、システム対応(バージョンアップ作業)
- 基礎控除額の変動に対応する
→従業員の収入に応じて基礎控除額が異なるため、計算ミスがないように確認。 - 令和8年分の源泉徴収税額表の基礎控除額の取り扱いを理解する
→令和8年分の源泉徴収税額表には、基礎控除の特例加算額が反映されていないため、年末調整で還付が大きく発生する可能性があることを従業員に説明できるようにしておきましょう。 - 対象者リストアップ
→19歳〜22歳の子どもがいる従業員の洗い出し
年収確認が必要な家族の把握
▶書類チェック
- 新しい「特定親族特別控除申告書」の提出確認
- 家族の年収証明書類の精査
納税者自身が気を付けること
▶書類準備
- 家族全員の年収を正確に把握
- アルバイト・パートの源泉徴収票を早めに収集
- 新しい申告書の記入方法を事前確認
▶タイミング
- 改正の施行日は令和7年12月1日
- 年末調整の申告は余裕を持って早めに
▶相談準備
- 複雑なケースは早めに経理担当者等に相談
- 家族構成や収入に変化があった場合は必ず報告
まとめ:控除関係のポイント
- 自身の収入と基礎控除額
ご自身の給与年収(額面)によって基礎控除額が変わるので、いくらになるのか確認しましょう。
所得税がかからないパート・アルバイトの壁が160万円に広がりますが、住民税(110万円)や社会保険(130万円、一部150万円)の壁は残っているので、注意が必要です。 - 扶養親族の収入と控除額
給与所得でいうと123万円以下までが扶養控除の対象になります。
もし扶養親族となる家族が新たに増えた場合、令和7年分のマル扶を再提出する必要があります。 - 学生のお子さんがいる家庭
19歳から22歳のお子さんがいる場合、給与年収が150万円までなら親の扶養から外れず、社会保険も扶養範囲内に収まる可能性があります。ただし、住民税は110万円の壁があるので発生します。
お子さんがアルバイトをしている場合は、今年の合計所得の見積額を正確に計算し、特定親族特別控除申告書に記入する必要があります。 - 配偶者がいる家庭
配偶者の給与収入が123万円以下の場合、「同一生計配偶者」として配偶者控除の対象になります。
納税者本人の年収によって控除額は変動するので、ご自身の年収を確認しましょう。
また、配偶者の年収が123万円から160万円の場合、「配偶者特別控除」が適用されます。
ただし、社会保険の壁は引き続き意識する必要があります。 - 住宅ローン控除を利用している家庭
2年目以降の住宅ローン控除は、税務署から送られてくる証明書だけで手続きができます。これまでの金融機関からの証明書は不要になるので、手続きが少し楽になります。
今回の年末調整は、たくさんの変更点があり、特に「年収の壁」を意識した改正が目立ちます。
経理担当者も納税者自身も、新しい制度をしっかり理解して、正しく申告することが大切です。
実務よもや話
税理士試験に出ない、年末調整。
私も、実務ではじめて対面したときは、苦戦しながら取り組みました。
税理士も、会社の経理担当者も、従業員のご家族の収入について正確なところを掴むのに苦労するのが現場ではないでしょうか。見積りと実際が違うパターンはもちろんのこと、去年と同じで扶養ですとだけ言われて収入は不明のまま、とか、年末調整の時期までに子供から収入の連絡がないのでわからない、とか。
今年はなにしろ『基礎控除』という収入がある人全員に関わるものが変わり、さらに扶養の範囲内となる所得の額が変わったのが大きいです。去年と同じ、ではなく、当人に他の収入があるか、家族の収入はいくらか、123万円を超えているか?といった確認がさらに重要になりそうです。
※本記事は2025年9月時点の法令・制度に基づいて執筆しています。内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の事情に応じた法的助言を行うものではありません。万が一、記事の内容をもとに行動された結果として損害などが生じた場合でも、筆者としては責任を負いかねますこと、あらかじめご了承ください。