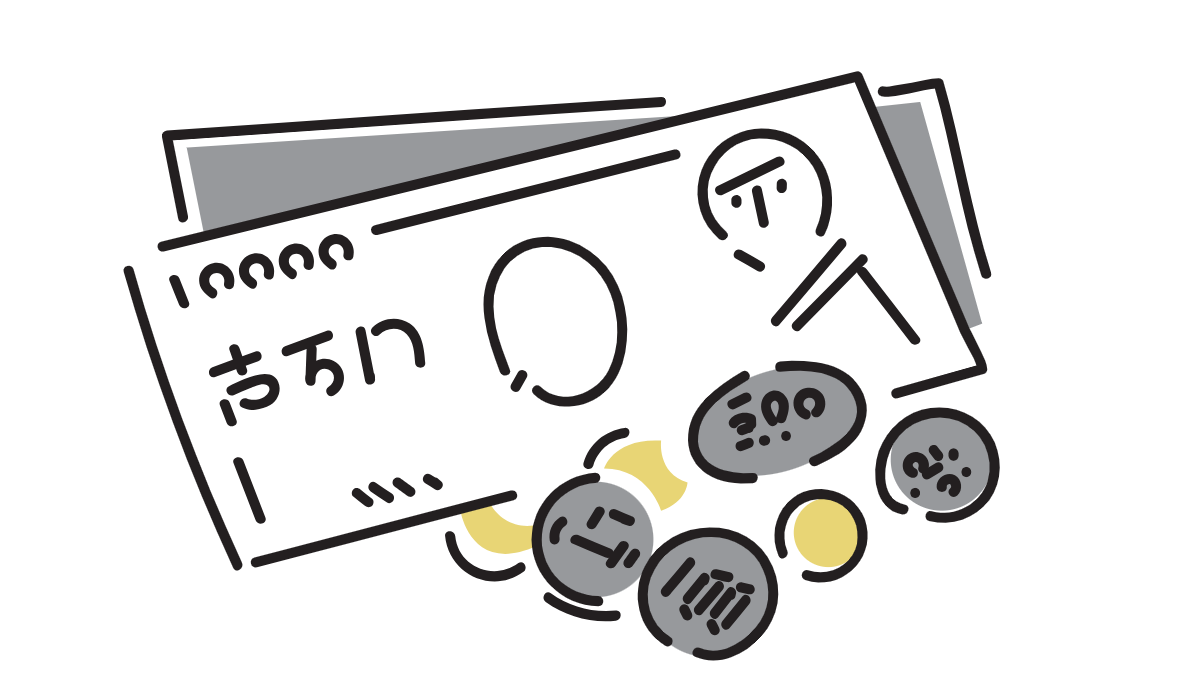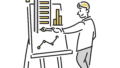質問:個人事業主が家族へ給与を払った場合、どのように払ったらよいですか?
個人事業主で、仕事が増えてきたので夫婦で一緒に仕事をしようと思っています。
お給料を払うとき、どのように支払らった良いですか?
答え:個人事業主が生計が一緒の家族にお給料を支払う場合、税務署に届出が必要になります。
個人事業主が家族にお給料を支払う場合、一般の従業員とは異なる手続きが
必要になります。その制度を活用して、家族への給料を経費にしていきましょう。
個人事業主の皆さんは、家族に仕事を手伝ってもらっている方も多いのではないでしょうか?
家族に支払うお給料を「経費」にできる特別な制度があります。
それが「青色専従者給与(あおいろせんじゅうしゃきゅうよ)」です。
上手に活用すれば、税金の負担を軽くすることができます。
今回は、この青色専従者給与について、解説していきます。
青色専従者給与ってどんな制度?
通常、個人事業主が生計を共にしている家族(配偶者や子ども、親など)に支払うお給料は、事業の経費にはできません。そこで特別に経費にするための制度が、青色専従者給与です。
特別な制度:「青色申告」をしている個人事業主さんだけが使える制度が「青色専従者給与」。この制度を使えば、家族に支払ったお給料を事業の「必要経費」として認められるようになります。
どんな家族が「青色専従者」になれるの?
●青色専従者として認められる条件
①青色申告をしている事業主と「生計を共にしている」配偶者やその他の親族であること。
②その年の12月31日時点で15歳以上であること。
③その年の半分以上の期間(6ヶ月超)、青色申告をしている事業の仕事に「専ら従事している」こと。
※「専ら従事している」とは、簡単に言うと、「他にメインの仕事はしておらず、その事業の仕事が主な活動である」状態を指します。例えば、他に会社員としてフルタイムで働いていたり、別の事業をメインでやっていたりする場合は、「専ら従事している」とはみなされません。
制度を使うために必要な手続き
青色専従者給与を適用するには、以下の手続きが必要です。
- 税務署に『青色申告の承認申請書』を提出し、承認を受ける(新たに青色申告を始める場合)
- 税務署に『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出する
提出期限:原則として、専従者給与を経費にしたい年の3月15日までです。その年の1月16日以降に新しく青色専従者を雇った場合や、事業を始めた場合は、雇った日または事業開始日から2ヶ月以内に提出しましょう。
記載内容:青色専従者に支払う予定のお給料の金額を記載します。実際に支払った金額がこの予定額を超えると、超えた部分は経費として認められないので注意が必要です。届出より少ない場合は問題ありません。 - お給料の支払いと帳簿の管理:実際に家族にお給料を支払い、帳簿に記帳・管理しましょう。
- 年間での金額変更には届出が必要:年度の途中で給与額を変更したい場合は、「青色事業専従者給与変更届出書」を税務署に提出する必要があります。
「青色専従者給与」を使えない人は?
- 「白色申告」をしている個人事業主(白色申告の場合は「事業専従者控除」という別の制度がある)
- 上記で挙げた「青色専従者」の条件を満たさない家族
⇒例えば、15歳未満の家族や、事業に専ら従事していない(他にメインの仕事がある)家族は対象外です。 - 実態のない勤務の場合
⇒たとえ家族であっても、当然ながら実際に事業に貢献する勤務実態がなければ、給与は経費として認められません。
メリット
・コストを抑えつつ信頼できる関係で働ける
・所得を分散して税金を減らせる
・家族も「給与所得控除」が受けられる
家族がお給料を受け取ることで、給与所得控除が適用され、その分の税金が安くなります。
例えば、夫婦で事業をしている場合。
・夫の所得が2,000万円ある
・夫1,000万円、妻1,000万円、と所得を分ける
この場合、後者の方が世帯全体で納める所得税・住民税が安くなることが多いです。
これは、所得税率が所得が多くなるほど高くなる仕組みになっているため、所得を分散することで税率の低い部分を多く使えるようになるからです。さらに、お給料を受け取る家族側も「給与所得控除」というものが受けられるため、二重の節税効果が期待できます。
デメリット・注意点
①お給料の金額は「妥当」であること
青色専従者給与に法律上の上限額はありませんが、仕事内容や労働時間に見合った「妥当な金額」である必要があります。あまりにも高額に設定すると、税務署に経費として認められないリスクがあります。他の従業員の給与とのバランス、仕事の内容、従事している日数時間、最低賃金(時給)などから、常識的に考えて高すぎない給与金額としましょう。
②世帯全体の手取りが減るリスクも
お給料を高く設定しすぎると、事業主の所得税は減りますが、家族側にかかる所得税や住民税、社会保険料が増え、結果として世帯全体の手取りが減ってしまう可能性があります 。
③配偶者控除・扶養控除との併用はできない
青色専従者給与を支払う家族は、配偶者控除や扶養控除の対象外になります。
お給料を払わず、配偶者控除をとった方が節税になった、というパターンもあります。
どちらが世帯全体で得になるか、よく比較検討することが大切です。
④実際に働いていないとダメ
実態のない勤務に対してお給料を出すことはできません。
⑤他の従業員とのバランスも重要
もし家族以外の従業員もいる場合、家族従業員との給与や待遇に大きな差があると、他の従業員の不満に繋がりかねません。勤務実態を明確にするために、出勤簿をつけるなどの配慮が必要です。
⑥正確な申告が必要
勤務実態が曖昧だと、支払った給与が不相当に高額と判断され、経費として認められない可能性があります。日頃から勤務状況や業務内容の記録を残しておきましょう。
年収の壁の問題
・年収160万円の壁(2025年分から)
青色専従者の年間給与を160万円以下に抑えれば、その家族自身には所得税がかかりません。これは給与所得控除(最低65万円)と基礎控除(95万円)を合わせた金額で、このラインが「所得税ゼロ」の目安となります。
・年収130万円の壁(2025年時点)
もし専従者の給与が年間130万円を超えると、社会保険の扶養から外れてしまいます。そうなると、その家族自身が国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を個別に支払う必要が出てきます。せっかく節税できたのに、社会保険料の負担が増えて世帯全体の手取りが減ってしまう、なんてことになりかねないので注意が必要です。
まとめ
青色専従者給与は、個人事業主が家族と協力して事業を進めながら節税できる、とても魅力的な制度です。お給料の金額設定や届出、社会保険の扶養など、いくつか注意すべき点もあります。ご自身の事業やご家族の状況に合わせて、最適な給与額を設定し、正しく制度を活用していきましょう。
実務よもや話
実際に専従者給与を払うようになった場合には、お給料が月額8万8千円以上だと、源泉徴収義務もあります。もちろん、年末調整(雇っている従業員の一年間の所得税の精算作業)もあります。事務負担という点でも、こまごま増えることがありますね。
働いているという実態があり、かつ家族全体としてお給料を払うことがプラスになるか(節税以外の点でも、仕事への意識、パートナーシップなど)、そのあたりを考慮して青色専従者という制度を取り入れていきましょう。届出を出しておいて、業務をしなかった年はゼロ(給与発生しない)でも問題ありません。経費にするには年の6カ月以上従事することが必要ですが、仕事をする年、しない年があっても良いのです。個人事業主の業務内容によっては、忙しい年だけ家族が手伝ってお給料を払うということも可能です。そのことを見越して、あらかじめ働いた場合の支給予定額を決めて届出だけ出しておく手もありです。
※本記事は2025年7月時点の法令・制度に基づいて執筆しています。内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の事情に応じた法的助言を行うものではありません。万が一、記事の内容をもとに行動された結果として損害などが生じた場合でも、筆者としては責任を負いかねますこと、あらかじめご了承ください。