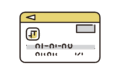質問:課税の繰り延べは効果がない、と言われました。その意味を教えてください。
節税のために、倒産防止共済に加入しようと検討しています。
課税の繰り延べしても意味はないよ、と言われましたが、その意味を教えてください。
会社に節税効果はないのでしょうか?
答え:納税の『先延ばし』なので税金負担を『なくす』効果はないです。が、会社にメリットが一切ないわけではありません。
課税の繰り延べとは、納税するタイミングを将来の先延ばしにする、ということです。
基本、払うトータルの税金は変わらないと思っていてください。
まず、手元資金を残すことを考え、キャッシュが減らない節税を(地道に)しつつ、
個々の事業者にとって有効なら『課税の繰り延べ』を使うようにしましょう。
倒産防止共済も、その年の税金を減らす(繰り延べる)以外のメリットを考え、
必要であれば課税の繰り延べかどうかに関係なく加入するのがおすすめです。
倒産防止共済や法人保険で節税をしよう。
こうした提案の多くは『課税の繰り延べ』と呼ばれる仕組みです。
一見すると税金が安くなるように見えますが、実際のところはどうなのか。
今回は、課税の繰り延べの効果と、もっと効果的な節税方法について解説します。
課税の繰り延べとは?
簡単に言うと……課税の繰り延べ = 税金の支払いを先送りすること。
つまり「今年払う予定だった税金を来年以降に回す」ということです。
納税を完全に回避するわけではありません。
納税のタイミングを将来に移動している、ということですね。
○よくある課税の繰り延べの例
倒産防止共済:掛金を払って税金を先送り→将来解約すると税金発生
法人の生命保険:保険料を払って税金を先送り→将来解約すると税金発生
4年落ちの中古車購入:早めに経費化→将来の経費が減って税金増加
○課税の繰り延べの仕組み
課税の繰り延べには、必ず経費となる『支払い』が必要です。
例えば、税率30%の会社が100万円の経費を支払うと、
まず、100万円のキャッシュが出ていく
⇒30万円の税金が減る(先送りされる)
⇒結果:手元のキャッシュは70万円減る
将来、その繰り延べ効果が戻ってくるときは、
100万円の収入が発生
⇒30万円の税金を支払う
⇒結果:手元のキャッシュは70万円増える
これが、課税のタイミングの先延ばしということです。
メリット
・手元資金を有効活用できる
・将来の税率変動に対応できる(後述します)
デメリット
○キャッシュフローが悪化する可能性
法人保険などで課税の繰り延べを行う場合、保険料の支払いにより手元資金が減少し、キャッシュフロー(入ってくるお金を出ていくお金の差)が悪化する可能性があります。単年ならまだよいですが、長期間支払う保険などは、支払いを続けられるか、その支払いが経営を圧迫しないかを考えましょう。
○解約時期によっては損することも
解約返戻金のある法人保険は、解約時期によっては払い込んだ保険料よりも受け取れる解約返戻金が少なくなる可能性があります。
○本質的な節税ではない
課税の繰り延べは税金の支払いを先送りするだけで、税金そのものがなくなるわけではありません。キャッシュフローの観点から見ると、最終的に税金は支払うことになるため、「節税」とは少し意味合いが異なります。
なぜ課税の繰り延べはあまりおすすめできないのか?
上記のように、繰り延べをした時点で、必ずキャッシュが減ってしまうからです。
「税金を払うくらいなら保険に入った方がマシ」と思うかもしれませんが、実際は、
保険に入る:手元のキャッシュ70万円減る
保険に入らず税金を払う:手元のキャッシュ30万円減る
と、手元資金のことを考えると、税金を払った方がお得です。
でも「絶対に節税ができない」わけではない
課税の繰り延べは、納税のタイミングが変わるだけで納税額が減ることは絶対にないのか?
というとそういうわけではありません。個人所得税や法人税は、所得が多いほど税率が高くなる仕組み(累進課税)になっているので、そこを使えたら、トータルでの節税効果があります。法人の場合は、利益800万円を境に税率が変わることがあります(対象外の法人もあり)。
つまり、税率が高い年に課税されるよりも、税率が低い年に課税された方が、同じ利益でもトータルの納税額が少なくなる可能性があります。その他、将来退職金が発生する年に解約して相殺するといった方法もあります。
計画的に繰り延べる(税率の変動を利用したり、出口戦略あり)であれば、メリットのある課税の繰り延べと言えます。
本当に効果的な節税方法とは?
課税の繰り延べも、会社の状況を考えて効果的に使うことはできますが、まずはキャッシュが出ていかない節税を優先しましょう。例えば、以下のような方法です。
- 除却・廃棄による節税(使わなくなった設備や機械を除却で経費計上)
- 回収不能な売掛金の処理⇒放置せずに早めに経費計上
- 在庫の評価損(型落ちや破損で通常価格で売れない在庫を、適切に評価損を計上)
- 未払金・未払費用の計上(給与も締日によっては大きな金額を経費計上できる、その他各種経費の未払分)
- 旅費規程の活用(出張日当を支給)⇒社長の所得税がかからない
などなど。
課税の繰り延べや節税が本業の目的ではない
税金の対策をする、今年の税金を減らす、それも大事な経理判断のひとつです。
しかし、それは経営の第一目的にはなりえません。何か経費を払うにしても、節税・課税の繰り延べ以外の有効な理由(事業にプラスになる)があるか、そこを検討しましょう。
まとめ
節税=税金を減らすこと
ではなく、
節税(の目的)=手元により多くのお金を残すこと
節税を優先しすぎて本業が疎かになったり、資金繰りが悪化しないようにしましょう。
優先順位としては、
- キャッシュが出ていかない節税(除却、評価損、未払計上など)
- 事業に必要な投資(設備投資減税制度の活用)
- 課税の繰り延べ
不必要な節税でキャッシュを減らすより、適正な税金を払って手元資金を残す方が、経営にとっては有効です。節税を検討する際は、「本当にキャッシュが増えるのか?」という視点で判断してみてください。
実務よもや話
ご質問にある、倒産防止共済。その名前の通り、本来の目的は『取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための資金調達手段』です。実際に利用を検討する(利用を決めた)事業者の方の目的は、節税(利益の圧縮)、資金繰り(掛金を積立てておき、必要なときに解約や貸付)、退職金や設備投資など、大きな支出のタイミングに合わせた「出口戦略」。それも、悪いことではありません。倒産防止共済には、以下のようなメリットがあります。
・連鎖倒産のリスクヘッジ
・無担保・低利率の資金調達
・簿外資産としての積立効果(課税の繰り延べながら貯蓄)
・解約手当金は退職金や設備投資などに充てることが可能
・事業承継時にも引き継ぎ可能
倒産防止共済に加入した際の、申告手続きの注意点もあります。適切に申告しないと、せっかく加入しても、税金計算上費用として認められない、なんて悲劇も起きてしまいます。以下、注意しましょう。
★別表の記載漏れがないように!
①資産計上方式を選ぶ場合:別表4・5での税務調整を忘れずにする
②費用計上方式を選ぶ場合:別表十(七)又は(八)と適用額明細書の添付が必須
なお、融資対策で決算書の見栄えをよくするなら、①の資産計上方式がおすすめです。
※本記事は2025年7月時点の法令・制度に基づいて執筆しています。内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の事情に応じた法的助言を行うものではありません。万が一、記事の内容をもとに行動された結果として損害などが生じた場合でも、筆者としては責任を負いかねますこと、あらかじめご了承ください。