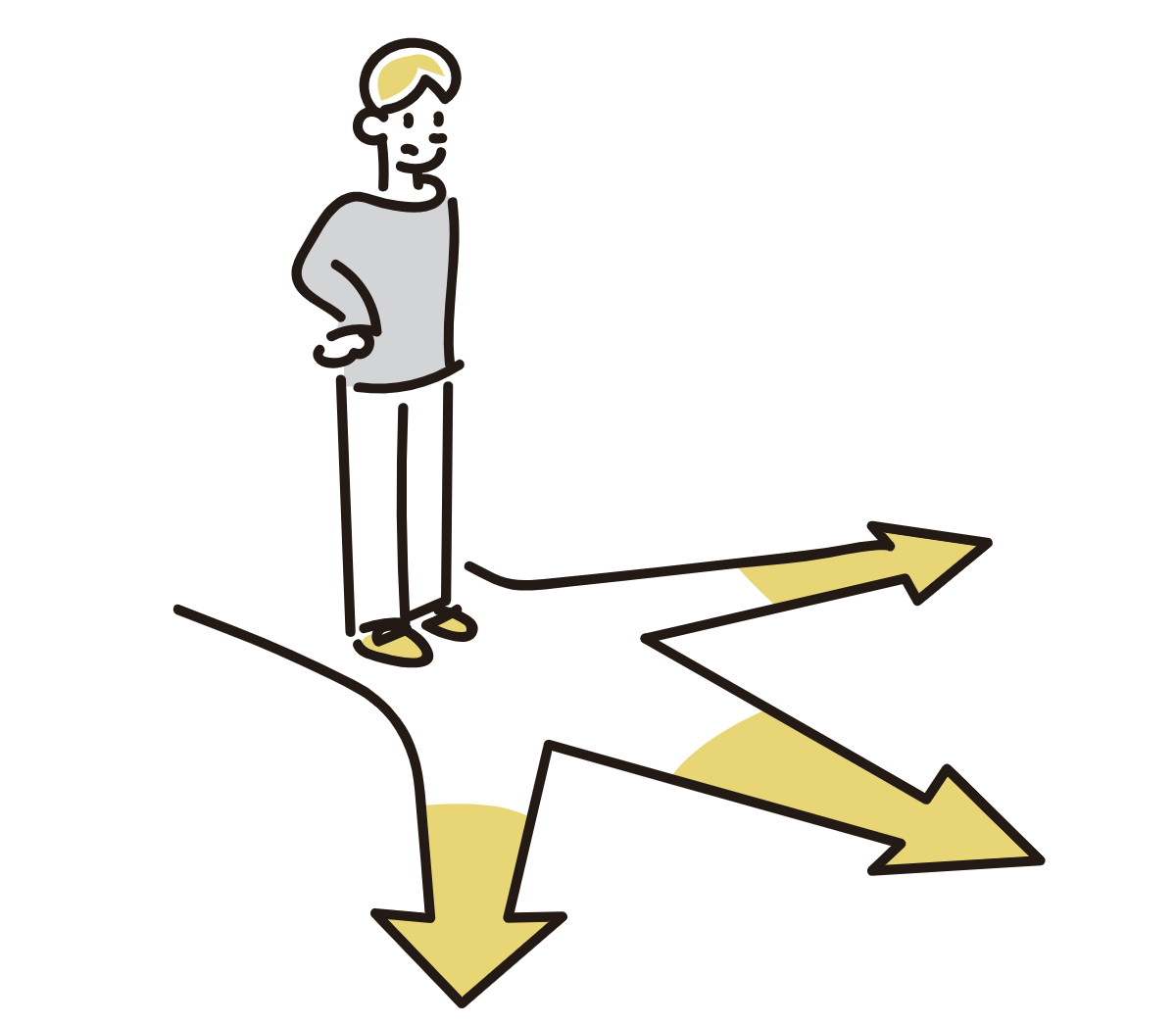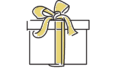質問:法人化するときに必要な準備、気を付けることを知りたい!
そろそろ法人化した方がいいのかな?と考えています。
なにから準備したらよいのか、法人化に必要な手続き、気を付けることを知りたいです。
答え:個人事業主との違い、メリット・デメリットを知ったうえで、まずは「なぜ法人化するのか?」をはっきりとさせましょう。
法人化を検討する際は、個人事業との違い(増える作業やコスト、メリットとデメリット)
を比較検討することが重要です。
そして「なんとなく」ではなく、「法人化する理由」をはっきりとさせましょう。
部分的にデメリットはあっても、○○○だから法人化する、とはっきりとしていれば、
覚悟を決めて法人経営をできます。
個人事業のように開業届を出して開業完了、というほどシンプルではないので、
専門家の力も借りつつ、必要な手続きを進めていく必要があります。
事業が順調に成長し、「そろそろ法人化した方がいいのかな?」と考えている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。法人化(法人成り)は、事業をさらに大きくするための魅力的な選択肢ですが、その一方で準備や手続き、費用など、知っておくべきことがたくさんあります。
法人化(法人成り)ってなに?
法人化(法人成り)とは、個人事業主として行っていたビジネスを、株式会社や合同会社といった「法人」として運営する形に変えることです。簡単に言うと、個人の名前でやっていた事業を、会社の名前でやるようになる、ということです。会社にすることで、ビジネスの信頼度がグンと上がったり、税金面でお得になったり、いろんなメリットがあります。事務手続きが増える、赤字でも税金がかかる、などのデメリットも。
事前に決めておくこと
法人化する際には、いくつかの重要なことを事前に決めておく必要があります。
①会社のタイプ(株式会社or合同会社)を決める
『法人=会社』と言っても、実はいくつか種類があるんです。個人事業主さんが法人化するときに、よく選ばれるのはこの2つ。
- 株式会社:一般的で社会的信頼度が高いイメージ。設立費用や手続きが合同会社よりもかかる。
- 合同会社:設立費用を抑えられ、手続きも比較的シンプル。近年選ぶ人が増えています。「グーグル」や「アップル」の日本法人も実は合同会社です。後述しますが、メリットだけでなくデメリットも理解しておくことが重要です。
どっちがいいの?と迷うと思いますが、それぞれの特徴をよく知っておくことが大事です。
特に合同会社は「手軽そう」というイメージだけで決めると、後で「あれ?」ってなることもあるので、しっかりチェックしておきましょう。⇒合同会社と株式会社の違いはこちら。
②会社の基本的な情報を決める
- 会社の名前(商号)は?(例:〇〇株式会社、合同会社△△)
- 会社の本拠地はどこにする?
- どんな事業を行う会社にする?(会社の目的)
- 誰が役員になる?(社長は誰か、他に必要な役員は?)
- 会社のお金はいくら用意する?(資本金)
- 会社の会計期間(いつからいつまでを1年にする?決算月は?)
など、会社の基本情報を具体的に決めていきます。
(参考)何人から法人化できる?
原則として1人からでも法人化は可能です。特に合同会社は一人社長さんにピッタリです。株式会社でも、取締役会を置かない形なら一人から作れます。
法人化の手続きの流れ
《会社を作る前の手続き(設立手続き)》
- 会社形態、会社の基本事項を決める:株式会社か、合同会社か。会社名や事業内容などを決定。
- 会社で使う印鑑を用意する: 代表者印(実印)、銀行印、角印などが必要です。
- 会社のルールブック(定款)を作る: 会社の憲法のようなもので、会社の基本的な情報を記載します。
- 定款の認証を受ける(株式会社の場合): 作成した定款を公証役場で認証してもらいます。合同会社の場合は不要です。
- 資本金を払い込む: 会社の元手となるお金(資本金)を銀行口座に振り込みます。
- 登記を申請する: 法務局に会社設立の登記を申請します。これで会社が正式に誕生します。
- 許認可の取得(必要な業種の場合): 飲食店や旅館業など、特定の事業を行う場合は、別途許認可の取得が必要になります。個人事業で持っていた許認可も、法人化したら取り直しが必要です。
《会社を作った後の手続き》
- 会社の銀行口座を開設する
- 個人事業を廃業する手続きを行う
- 個人事業の資産や負債を会社に移す手続きを行う
- 個人から法人へ名義変更を行う
- 会社の登記簿謄本や印鑑証明書を発行する
- 税務署など各機関に会社設立の届け出を提出する
- 労働保険・社会保険に加入する手続きを行う
- 税理士を雇うことを検討する: 会社の税務は個人事業よりも複雑になるため
法人化でかかる費用
法人化には、初期費用と、会社を維持するための費用がかかります。
《初期費用(設立費用)》
- 株式会社: だいたい22万円~26万円くらいが目安です。
- 登記の費用(登録免許税):最低15万円(資本金×0.7%)
- 定款をチェックしてもらう費用:約5.2万円
- 印紙代:4万円(電子定款なら不要)
- 会社用のハンコ代:1~2万円
- 合同会社: だいたい10万円くらいが目安です。
- 登記の費用(登録免許税):約6万円
- 会社用のハンコ代:1~2万円
- ※合同会社は定款チェック費用が不要なので、グッと安くなります!
専門家(司法書士さんなど)にお願いするなら、さらに5万~15万円くらいかかることが多いです。
《維持費用(毎年かかる費用)》
- 法人住民税の均等割: 赤字でも毎年支払う必要がある税金です。
- 社会保険料の会社負担分: 従業員だけでなく、社長自身の社会保険料の一部も会社が負担します。
- 税理士などの専門家への報酬: 税務申告などが複雑になるため、専門家に依頼するケースが多いです。一人会社や事業内容がシンプル(複雑な原価計算や特殊な消費税計算がない)場合で、経営者の方が経理や税務への意欲がある場合は、自分で申告まで行う場合もあります。
法人化後の義務
法人化すると、個人事業主の頃にはなかった義務も発生します。
- 社会保険への加入義務: 社長自身も加入することになります。
- 労働保険への加入義務: 従業員を1人でも雇用したら、労働保険(労災保険、雇用保険)への加入も義務です。労災保険は全額会社負担です。
- 会計や事務手続きの負担増: 税務申告や各種届出など、個人事業主に比べて複雑で煩雑な事務作業が増えます。
- 赤字でも税金がかかる: 法人住民税の均等割は、会社が赤字であっても発生します。
法人化のメリット・デメリット
《メリット》
- 社会的信用が高まる: 会社として認められるため、取引先からの信用が得やすくなり、大きな仕事につながったり、銀行から融資を受けやすくなったりします。
- 節税になる可能性がある: 事業の利益が増えると、個人事業主の所得税よりも法人の法人税の方が税率が低くなるケースがあり、税金が安くなることがあります。
- 経営者が生活費(給与)を経費にできる:個人の場合、事業主の生活費=取分は給与(経費)にはできません。法人にすると、経営者は役員報酬を「定期同額給与」や「事前確定届出給与」として支給すれば、経費にできます。親族を役員にした場合も同じです。
- その他経費の範囲が増えることによる節税効果:例えば、自宅を「役員社宅」として契約すれば、家賃の一部を法人経費にできたり、「出張旅費規程」を整備すれば、役員にも非課税で出張手当を支給可能。
- 赤字の繰越期間が長い:個人事業主は3年、法人は最大10年(2025年現在)まで赤字を繰り越して将来の利益と相殺可能です。
- 責任の範囲が限定される(有限責任): 万が一事業がうまくいかなくても、会社に出資した金額以上の責任を負う必要がありません。個人事業主は無限責任なので、ここが大きな違いです。
- 資金調達の選択肢が増える: 銀行融資や補助金・助成金なども受けやすくなります。
- 人材を確保しやすくなる: 社会保険加入などの福利厚生を整えられるため、従業員を雇いやすくなります。
- 決算月を自由に決められる: 事業の繁忙期を避けて決算月を設定できるため、事務作業の負担を分散できます。個人は、一律で1~12月が事業年度です。
《デメリット》
- 設立や維持に費用がかかる
- 赤字でも税金がかかる
- 社会保険への加入が義務になる
- 会計や事務手続きが複雑になる
- 会社の利益を自由に使えない:会社の利益は会社のものであり、個人的に自由に使えません(個人と会社の財布は完全に分ける)。役員報酬として受け取るには、変更に条件があったりします。
- 交際費に上限がある:中小法人でも年間800万円まで。個人事業主にはこのような制限がない。
- 会社を畳むのにもお金がかかる:もし事業を辞めることになっても、個人事業の廃業より、会社を解散する方が費用も手間もかかります。
- 精神的なプレッシャーが増えることも…:社会的な信用が高まる分、「ちゃんとしなきゃ」というプレッシャーを感じたり、税務調査が気になるなど、精神的な負担が増えることもあります(個人事業主にももちろん税務調査はありますが、法人の方が調査対象にはなりやすい)。
合同会社とは
《株式会社との違い》
合同会社と株式会社の根本的な違いは、「所有と経営が分離しているかどうか」です。
- 株式会社: 出資者(株主)と経営者が異なるメンバーで構成され、所有と経営が分離しています。
- 合同会社: 出資した人が会社の所有者(経営者)となり、所有と経営が一致します。
その他、合同会社には以下の特徴があります。
- 生じる責任は有限責任のみ
- 出資額に関わらず1人1票の議決権がある(定款で変更可能)
- 役職(役員)の任期が定められていない
《合同会社はやめておけ、と言われるのはなぜ?》
設立費用が安くて魅力的!な合同会社ですが、インターネットで検索すると「合同会社はやめとけ」なんて言葉も出てきます。実は、手軽さの裏には注意すべき点も隠れています。
- 「株式会社じゃないんだ…」社会的信用度が低め?
合同会社は株式会社に比べて知名度がまだ低いため、「この会社、大丈夫かな?」と一部の取引先や銀行から思われてしまう可能性も。採用活動でも、株式会社の方が安心感があると感じられることがあります。 - 資金調達が難しいかも
株式会社は「株」を発行して投資家からお金を集めることができますが、合同会社にはその仕組みがありません。国や自治体の補助金・助成金、銀行からの融資が主な資金調達方法になるので、選択肢が限定的になります。 - 上場は無理?
将来的に会社を大きくして、株式市場に上場したい!という夢があるなら、合同会社では不可能です。 - 「利益の分け方」でモメることも…
株式会社は出資した割合で利益を分けますが、合同会社は「自由に決めていいよ」というルールなんです。これは良い点でもありますが、社員同士で不公平感が出ると、トラブルに発展してしまうことがあります。
《相続で「まさか?!」》
もし会社を誰かに引き継ぐことになった時も、合同会社と株式会社では大きな違いがあります。
- 株式会社の「株」:親が持っていた株は、子供がそのまま引き継いで、会社の持ち主になれます(特別なルールがない限り)。
- 合同会社の「持分」:親の持分を子供が引き継ぐことはできます。でも、持分を相続したからといって、自動的に会社の「社員」(=経営者の一員)になれるわけではありません。他の社員全員の同意が必要になります。もし同意が得られないと、子供は会社の経営には関われず、出資金を払い戻してもらうだけ、なんてことも。
だから、合同会社を検討するなら、将来誰かに事業を継がせたい場合にどうするか、事前にしっかり話し合って、会社のルールブック(定款)に明記しておくことが大事です。
法人化した方がいい人とは?
- 売上や利益が大きく増えてきた人: 特に、個人事業の所得が800万円を超えた場合や、売上高が1,000万円を超えた場合は、節税効果が期待できるため法人化を検討すると良いでしょう。
- 社会的な信用を高めたい人: 大企業との取引や、融資を受けたいと考えている人。
- 従業員を雇う予定がある人: 社会保険の加入が必須になるため、会社として雇用環境を整えたい場合。
- 「国の補助金や助成金に興味がある」:法人の方が申請できるものが多かったり、審査が通りやすかったりします。
- 「将来、家族に事業を引き継ぎたい」:法人にしておくと、事業承継の計画が立てやすくなります。
- 「きちんと会社の仕組みを作って、本気でビジネスを大きくしたい!」:経営への意識が高まり、事業拡大への意識も高まります。
法人の中でも合同会社に向いているケース・業種
- 初期費用を抑えて小規模スタートをしたい事業者: 設立費用が安く、手続きも比較的シンプルなため、スモールスタートを切りたい場合に適しています。
- 節税効果を求める個人事業主: ある程度の利益が見込める個人事業主であれば、合同会社でも節税メリットを享受できます。
- 小規模なBtoC事業(対個人の事業): 顧客が法人形態をあまり気にしない業種(例:ウェブ制作、コンサルティング、個人向けサービスなど)では、社会的信用の低さが大きな問題にならないこともあります。
法人化しない方がいい人(法人化しなければ……と後悔しやすい人)
- 「なんか良さそうだから」と、特に法人化する理由の薄い人
法人化のデメリットや義務を知っていかないと、後で「こんなはずじゃなかった…」と後悔することに。 - 「まだ売上も利益も少ない」
法人化の節税メリットは、ある程度の利益が出てからでないと享受しにくいです。赤字だと、かえって負担が増えることも。 - 「事業計画や資金繰り計画、経理や事務作業が大の苦手!」の人
法人化すると、これらの業務が増やえます。専門家に頼むこともできますが、自分でやるべきこともあるので、ある程度の作業増は必須です。
法人化のメリット(コスト面含む)<増える負担、専門家へ払う費用
という場合は個人事業主のままでいるという選択肢もありです。
実務よもや話
単純に、メリットデメリットを比較して決める、ということでもないのが、実情だと思います。
そもそも、法人でないと取引ができない、契約ができない、という業界もあるので、その場合は事業を立ち上げる時点で、個人ではなく法人から始めるとうことになります。
はじめにも書きましたが、なぜ法人化するのか、その目的が明確、かつ長期的に経営への意欲を失わないものであることが、多少のデメリットはデメリットとならず、経営を継続していけると思います。反対に、個人事業主を続けるという決断も同様で、そこに自分なりの明確な理由があれば、個人事業主として続けていくことがよいでしょう。一般的なメリットデメリットではなく、一点突破でも、明確な思いがある人はやはり強い、と感じます。
※本記事は2025年7月時点の法令・制度に基づいて執筆しています。内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の事情に応じた法的助言を行うものではありません。万が一、記事の内容をもとに行動された結果として損害などが生じた場合でも、筆者としては責任を負いかねますこと、あらかじめご了承ください。