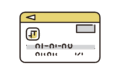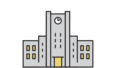質問:会社で犬を飼っています。エサ代や病院代を経費にできますか?
従業員の癒しを目的として、会社で犬を飼っています。
エサ代や病院代を経費にしたいのですが、大丈夫でしょうか?
答え:『癒し目的』だと経費計上は難しいです。ペット関連費用は、事業に関連することが明確であれば、経費として認められます。
残念ながら、『癒し目的』だと事業に明確に関連していると言うのがちょっと難しいため、
経費として計上することが認められにくいです。
同じペット関連でも、会社の広告塔(マスコミキャラクター、看板犬・猫)や病院の
セラピードッグということであれば、事業との関連が明確なので経費にできます。
「ペットのエサ代や病院代、経費になるの?」
結論から言うと、「条件次第では経費にできます!」。
ただし、なんでもかんでもOKというわけではないので、その条件や注意点を解説します。
経費になるかの分かれ道
経費の基本のキ。ペットに関する費用を経費にできるかどうかの最大のポイントはズバリ、
そのペットが事業にどれだけ関係しているか?
「関係しています!うちの犬はいつもオフィスで癒しを提供してくれてるんです!!」
……残念ながら、個人的な癒しや社員のモチベーションアップが主な目的だと、明確な関連が認められにくいので、経費にするのは難しいです。カギは、
「事業のために必要である(具体的な関連がある)ことを、第三者に説明できるか?」
「その説明を誰が聞いても納得できるか(自身も後ろめたいところがないか)」
ペット関連に限らず、事業の費用として計上できるかを考えるときこれが基本です。
こんなケースならOKです!
では、具体的にどんな場合にペットの費用を経費にできるのでしょうか?
① ペット関連のビジネスを運営している場合
「ドッグカフェ」「猫カフェ」など、動物との触れ合いを目的とするビジネスでは、動物がいないと商売になりません。事業との関連性100%ですよね。だから、購入費用からエサ代、病院代、保険料まで、飼育にかかる費用全般が100%経費として認められます。当然と言えば当然です。
② 会社の「顔」として活躍!広告塔やマスコットの場合
「看板犬・猫」「猫駅長」「社員犬」などがこれにあたります。会社のホームページやSNS、YouTubeなどでそのペットを宣伝に利用していると、「広告塔」としての経費が認められる可能性が高まります(1回限りの出演とかではなく、継続的に、積極的に出している場合)。売上や集客に必要なペットということですね。
③ 「番犬」や「応接室のアクアリウム」で会社の印象アップ
オフィスで犬や猫、熱帯魚を飼う場合も、事業関連の目的がはっきりしていれば経費にできます。
例えば、お客様をお迎えするロビーや応接室に置かれた熱帯魚の水槽。「顧客からの印象が良くなる!」という目的があれば、会社の備品として必要経費と認められることが多いです。また、防犯対策として「番犬」を飼育する場合も経費計上が可能です。
④ その他の事例
病院や老人ホームなどで活動する「セラピードッグ」や「セラピーキャット」。
SNSなどで活動し収益を生む「ペットインフルエンサー」。など。
ペット費用は帳簿にどう書けばいいの?
経費にできることが分かったら、それを帳簿に記録します。
そこで悩むのが「帳簿にどうやって書けばいいの?」という点ですよね。
帳簿にのせる「名前」(勘定科目)について解説します。
① ペットはまさか!?の「備品」
驚かれるかもしれませんが、ペットの購入代金は税務上「備品」として扱われるんです。
「生物」という勘定科目もあるのですが、これは1体30万円以上の、主に農業や畜産業で生産活動を行う目的で飼育される生き物です。牛や馬、豚、ヤギなどですね。ここまで説明してきたような、ペットビジネス、広告塔やセラピードッグなどのペットは基本的に「備品」とします。間違えて「生物」を使わないように注意してください。
〇10万円未満なら、「消耗品費」として一括経費OK!
○30万円未満なら、特例で一括経費OK!
青色申告をしている個人事業主や中小企業の場合、10万円以上30万円未満の備品は、年間合計300万円を超えない限り「少額減価償却資産」という特例を使って、購入した年に全額をまとめて経費にすることができます。
○30万円超えたら減価償却
30万円を超える高額なペット(例えば、珍しい種類の動物など)を購入した場合は、固定資産(備品)として計上して、購入費用を何年かに分けて少しずつ経費にしていきます。税法で定められた「使える年数」(耐用年数)は以下の通りです。
魚類:2年
鳥類:4年
その他(犬や猫など):8年
※実際にはもっと長く生きることが多いですが、税法ではこうなっています。
② エサ代や病院代は?
日々のエサ代やペットシーツ代などは、「消耗品費」として計上するのが一般的です。
病院代は、その動物の飼育目的によって「広告宣伝費」「販売促進費」などを使っても良いでしょう。
「動物管理費」といった独自の科目を使って、そこに関連するものをまとめることもできます。
実は、これらの勘定科目には厳密な決まりがありません。後から見て分かりやすいように、かつ、毎年同じ科目で記録しておくことが大事です。もし税務調査で勘定科目について指摘されても、「わかりました。次回の申告から指摘された科目で処理します」と言えば大丈夫です。
税務調査で慌てないために
「経費にできるのは嬉しいけど、税務調査がちょっと怖いな…」と思った方もいるでしょう。
税務調査官に堂々と説明できるコツがあります。
①「事業との関連性」を証明する記録
もっとも重要なのが、これです。例えば、看板犬なら、会社のHPやSNSで活動している写真、お客様との交流の記録など、「この動物が事業にどう貢献しているのか?」を具体的に説明できる材料を用意しておきましょう。
②レシート&明細の記録
どんな経費でも同じですが、領収書や明細書はきちんと保管し、何のために使った費用なのかを明確に記録しておくことが不可欠です。
実務よもや話
費用にできるかどうかを考えるときに出てくる『事業関連性』。
これはとても重要であり、かつ難しい論点です。
同じようなお金の使い方でも、事業の内容によって関連があるなしが変わりますし、社会通念上(常識で考えて)妥当ではない、関連がないだろうと言われても、経営者からしたら「ある」と言いたくなることもあります。
「従業員のためのスポーツジム費用が福利厚生費として認められて、なぜ癒しの犬が認められないのか?!」
そう言いたくなる気持ち、わかります。スポーツジムで汗を流して心身の健康を保ち、仕事へのモチベーションアップ!となる人もいれば、犬に癒されてモチベーションアップ!という人もいる。
「一般的に癒し犬が認められることは少ないから、どうしてもダメなのか???」
絶対に、100%、120%否認ということもありません。
実務で癒し犬を飼っている方の経理処理をしたことはいまのところありませんが、理屈で考えると、その効果(従業員への効果)を証明する記録をすることで、福利厚生として証明できる可能性もあると思います。例えば、
・全従業員が接することができる場所で飼育していること
・従業員が当番で世話をしている記録
・従業員アンケート(そのペットを飼ったことによるプラスの効果や感想)
・そのペットが社内で生活し、従業員と触れ合っている様子の記録や発信
・社内規定に明記する
こういったことをきちんと記録していくことです。
そして何より重要なのは、まずは経営者の方が胸を張って、後ろめたい点なく「従業員のために飼っています。その理由と効果を説明できます」と言える状況であるかどうか。それをまずは考えてみましょう。どんな経費であっても、「会社の事業のため(私的な目的ではない)」と言えるか。スタートはそこです。そして、プライベートとの境界線が曖昧ではないか(自宅兼事務所で飼っている=実質家族で飼っている犬は✕)、経理処理に一貫性があるか(利益が多い年だけ経費にしているといったことはNGです)、など、経費として認められる条件をひとつひとつチェックしていきましょう。
※本記事は2025年8月時点の法令・制度に基づいて執筆しています。内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の事情に応じた法的助言を行うものではありません。万が一、記事の内容をもとに行動された結果として損害などが生じた場合でも、筆者としては責任を負いかねますこと、あらかじめご了承ください。