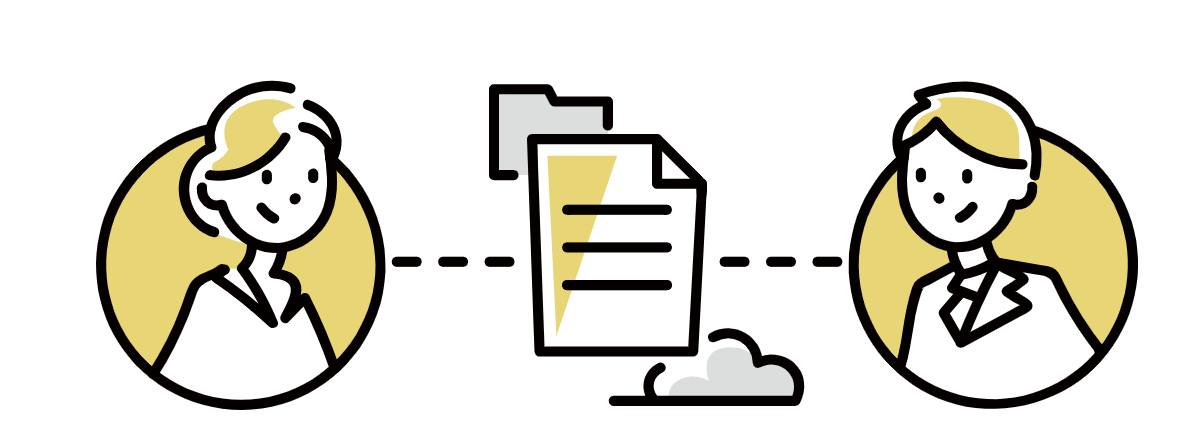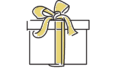質問:電子帳簿保存法の基本と、改正について教えて
いまさらですが、電帳法(電子帳簿保存法)とはなんですか?
自社の請求書は紙で送っています。会計ソフトは使っています。
あらためて、関係あることを教えてください。
答え:これまで紙で保存していた帳簿等をデータ保存するルールです
これまで紙で保存していた税金に関わる帳簿や書類を、電子データで保存できるように
したり、また、そうしなければならなかったりするためのルールです。
受領する請求書などに、紙ではなくデータのものがあれば、データ保存が義務になります。
基本
「電子帳簿保存法(電帳法)」という言葉はきいたことはあるけれど、
難しそう…」「うちには関係ないかな?」と思っている方もいるかも多いかもしれません。
実は法人や個人事業主としてビジネスをしている方なら、ほとんど全ての方に関係する
大切な法律です。令和7年度税制改正もあります。
まず、電子帳簿保存法、これだけは知っておきましょう。
電帳法は新しい法律と思いきや、実は1998年7月に施行されており、
時代の流れに合わせて何度も改正が繰り返されてきました。
電帳法には大きく分けて3つの区分があります。
①電子帳簿等保存
会計ソフトなどで最初からデジタルで作った帳簿や書類(例:仕訳帳、パソコンで作成した請求書
の控えなど)を、データのまま保存すること。
②スキャナ保存
紙で受け取った書類(例:紙の領収書、請求書など)をスキャンして、画像データとして保存すること。
③電子取引 ※義務!
インターネットやメール、クラウドサービスなどを通じてやり取りした取引データ(請求書、領収書な
ど)を、そのまま電子データで保存すること。
特に重要なのは③電子取引です。なぜならば……
「電子取引データ」の保存は、ほとんどの事業者で「義務」だからです!
2024年1月1日以降、電子データでやり取りした取引情報(請求書や領収書など)は、
電子データのまま保存することが完全に義務化されました。
つまり、メールで送られてきた請求書や、クラウドサービスからダウンロードした領収書などは、
紙に印刷して保存するだけでなく、電子データのまま保存することが必須になった、ということです。
「まだ対応できていない…」という方もいるかもしれませんが、放置しておくと法律違反となる可能性
もあるので、きちんと対応することが重要です。
まず、電子取引とは?について簡単に説明します。
《電子取引の具体的な例》
・メールにPDF添付された請求書
・Amazonなどのサイトで購入し、請求書をダウンロード
・クラウド請求書サービス
・ペーパーレスFAXで請求書等をPDFで受信
Amazonなどのサイトで事務用品や消耗品を買っているという方は多いと思うので、電子取引が
ゼロです、という方が少ないかと思います。
いずれも、紙では受け取っていない、というのがポイントです。
もし、同じ内容の請求書をデータと紙の両方でもらっていたら、紙保存のみでも大丈夫です。
では、具体的にどう保存すればいいのか?
電子データを保存するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
①真実性の要件(改ざんされていないこと)
「このデータは改ざんされていない」と証明できること。
②可視性の要件(いつでも確認できること)
保存したデータをいつでもすぐに確認できて、必要な情報が探せる状態にしておくこと。
具体的には、以下の項目で検索できるようにしておく必要があります。
*取引年月日
*取引金額
*取引先
*日付または金額の範囲指定で検索できる
*2つ以上の任意の検索項目を組み合わせて検索できる
これらは「ちょっと面倒だな」と感じるかもしれませんが、会計ソフトやデータ管理システムが、
これらの要件を満たすような機能を提供していますので、活用を検討してみてください。
任意の①電子帳簿等保存と②スキャナ保存はどうしらよいのか
一方で、自分で作った帳簿や書類を電子データで保存する「電子帳簿等保存」や、紙の書類をスキャン
して保存する「スキャナ保存」は、今のところ「任意」です。
つまり、「やってもやらなくてもOK」ということですね。
以前は、これらを行うには事前に税務署に届け出が必要でしたが、2022年1月1日以降は届出が不要
になったため、導入のハードルはぐっと下がっています。
Q.導入するメリットは?
紙と電子データが混在すると、管理が複雑になり、紛失や見落としのリスクも高まります。
できる限り「全てをデータ化して保存する」という方向で導入することで、そのリスクを小さくする
メリットはあります。
導入コストや運用負担というデメリットがメリットを上回る以下のような場合は、現段階では無視
しても良いでしょう。
①体制が整っていない事業者
• 「周りがやっているから」「ソフトに機能があるから」となんとなく導入を検討している
• 社内体制や業務フローが整っていない
➡ 中途半端な導入は、かえって業務が煩雑になり、税務調査で不利になるリスクも。
②紙の書類が少ない・取引量が少ない事業者
• 年間の請求書・領収書の枚数が少ない
• 経理処理を年に1回、申告前にまとめて行っている
• 紙の保管スペースに困っていない
➡ 紙で保存しても手間が少なく、電子化の恩恵が小さい。
③経理担当が1人(または社長本人のみ)で、業務負担が大きい事業者
• 小規模事業者やフリーランス
• 経理・営業・現場をすべて1人でこなしている
• 新しい制度を理解・運用する余裕がない
➡ スキャナ保存の要件(タイムスタンプ、検索機能、保存期限など)を守るのが現実的に
難しい。
令和7年度税制改正のポイント
さて、2025年度(令和7年度)税制改正大綱の中で「電子帳簿等保存制度の見直し」が決定されました。
これは、すでに義務化されている「電子取引データの保存」に関するもので、特に「重いペナルティ」と
「優遇措置」に影響があります。
①不正があった場合のペナルティ軽減(重加算税の加重措置の除外)
もし電子取引データに関して「ごまかし」や「不正(隠蔽・仮装)」があった場合、通常は重加算税
(重いペナルティ)が10%加重されることになっています。
しかし、2027年1月1日以降(令和9年1月1日以後)は、国税庁長官が定める基準に適合したシス
テムを使って、適切な方法で電子取引データを保存している場合には、この10%の加重が適用され
なくなります。これは、デジタル保存に取り組んでいる事業者への「ご褒美」のようなものですね。
②青色申告特別控除65万円の適用要件の追加
個人事業主の方にとって嬉しいのが、青色申告の「特別控除65万円」の適用要件に、新たな選択肢
が加わることです。
これまでは、優良な電子帳簿を使っているか、e-Tax(電子申告)を行っていることが条件でしたが、
2027年分以降の所得(令和9年度以降)からは、上記の「国税庁長官が定める基準に適合したシステ
ム」を使って、要件通りに電子取引データを保存していれば、65万円控除が受けられるようになります。
結論:まずは、義務となる電子取引データの保存を確実にクリアしましょう
ここまで電子帳簿保存法について見てきました。
一番大切なポイントは、
「電子取引データの保存は、ほぼ全ての事業者にとってすでに義務化されている」
ということです。ここは「知らなかった」「まだできていない」では済まされない部分なので、まずはここか
ら確実にクリアしましょう。
そして、任意である「電子帳簿等保存」や「スキャナ保存」については、ご自身の電子取引の現状を把握
し、業務の流れを見直し、必要であればデータ保存システムの導入を検討することも重要です。
電帳法はこれからも時代に合わせて改正されていくと思われますので、
やるべきところ、できるところから少しずつでも良いので、導入していきましょう。
実務よもや話
任意のルールは、どれくらい導入されているのか?
具体的な統計はありませんが、ざっくりどちらが導入が多いかというと、
電子帳簿保存(帳簿・決算書)> スキャナ保存
です。
現時点では、電子帳簿保存の方が導入しやすいですね。
会計ソフト(特にクラウド)を使えば自動的に電子帳簿保存の要件を満たすことが多いからです。
実際に導入している中小企業・個人事業主も多いと感じます。
一方スキャナ保存は、「ただスキャンすればOK」ではないので、ハードルが高いです。
あとは、紙のものをわざわざスキャンするのはどうか?とあまりメリットを感じられないというのも
あると思います。紙でもらったら、紙でいいよね、となるのはわかります。
紙レシートを撮影(スマホ)又はスキャン、保存という手間を考えると、私自身は導入していません。
スキャン保存をするなら、紙書類のやりとりをなくした方がいいなと思います。
(といっても、自分が作成する請求書はともかく、相手先についてはコントロールできないですが)
いずれにしても、任意のものについては、
自社がやりやすい方法を選択でよいかなと思います。
義務化されたらそのとき対応する、で良いかと思います(個人事業主、中小企業については)。
※本記事は2025年7月時点の法令・制度に基づいて執筆しています。内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の事情に応じた法的助言を行うものではありません。万が一、記事の内容をもとに行動された結果として損害などが生じた場合でも、筆者としては責任を負いかねますこと、あらかじめご了承ください。